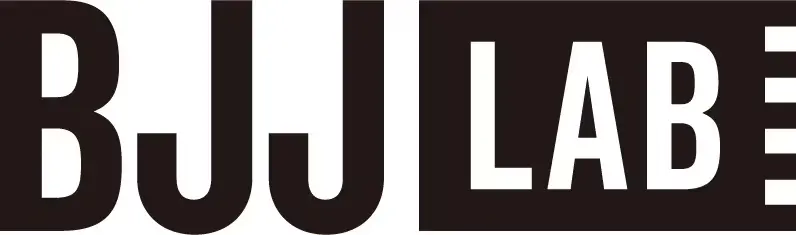「青帯になってから上達を感じない」「試合にも勝てない……」
という話をよく聞きます。ふり返ると、僕も青帯1年目は連敗つづきでした。
先日の文京柔術スパーリング(練習会)で、全日本マスターに出場した2名の方と話しました。二人とも「白帯では負けたことないんですけど、青帯は難しいですね」と言っていました。
BJJ LABの下前さん(現在茶帯)も青帯1年目はほとんど勝てなかったと言っていました。
同じ悩みを抱えている人は多いです。一競技者として自分が取り組んでよかったことを書きます。
延藤素康。BJJ LABのマーケティング担当。教育業界でウェブマーケターをやっています。柔術歴は3年。青帯1年目は連敗を重ね、最近ようやく勝てるようになる
青帯の伸び悩み blue belt bluesとは?
「白帯が一番しんどい」はほぼ常識と言えるし、青帯になることは柔術において最初の達成と言えます。しかし、その達成直後にもっと大きな壁の存在に気づき、どんよりすることになります。
英語圏の柔術家の間では「blue belt blues」と呼ばれているそうです。
僕が感じたblue belt bluesは、このあたり。
- 手加減してもらえなくなる。
- 紫帯とのレベル差を改めて知り、絶望を感じる。
- 柔道など他競技経験者が青帯から試合に参入してくる。
- フィジカル強/体重の重い白帯に押し込まれることはよくある。
- 練習時間に比例して上達しない
この中で一番しんどいのは「白帯の頃に比べて、練習回数に比例して上達しない」ことでしょう。
僕は1年3ヶ月で伸び悩みを感じた
僕は2022年3月に始めて、2023年2月に青帯をいただきました。
2023年4月に青帯デビュー戦(アダルト)を迎え、50/50になり5分近くフットロックを狙われつづけました。白帯の展開と明らかに異なり、青帯で勝ち上がるのはしんどいなと思いました(この時の対戦相手はすでに黒帯になっています)。
JBJJFのYoutubeのメンバーシップに加入している方は、試合の様子をご覧いただけます。
そこから長い敗戦期間が始まります。8月には10-0から一本を取られたり、9月にはループチョークで絞め落とされたり、まあさんざんでした(笑)

ノーギでの成績はそれなりに良かったものの、ギの練習を本格化してまだ半年しか経っておらず。ギはずっと勝てませんでした。ジムでも紫帯の人には歯が立たないし、青帯どころか白帯の出稽古の人にやられることもありました。
竹浦さん「成長していないわけではない」
竹浦さんと知り合って間もない頃、「初めて成長の鈍化を感じます」と相談しました。
それに対して「青帯になると成長が止まっていると感じる人が多いですね。でも実際に成長していないわけではありません」とアドバイスをもらいました。
よく考えると、 柔術では青帯になるまで数年、紫帯だと5年くらいかかると言われます。1年ちょっとならわからないことも多いだろうと割り切ることにしました。
割り切るといっても惰性で練習してはダメだと思ったので、より意識的に取り組むことにしました。そこからおおよそ半年でblue belt bluesから抜け出すことができて、3年たった今も日々伸びを感じながら練習に励んでいます。
青帯1年目でやってよかったこと
僕がやったことについて振り返ります。青帯1年目の方の参考になれば嬉しいです。
①教則動画をたくさん見る
柔術の世界は広大です。青帯1,2年目だとまだまだ基本的なテクニック、戦略の知識が足りていません。
知識が増えて相手が何を狙っているのかを知ることができれば、守れることが増えます。相手の得意を避けて戦うことができれば帯上の人とも戦えます。
できないことはたくさんあるし、青帯で消化することは無理なので、諦め(後回し)も必要だと感じます。
たとえば僕がトレアドールパスを使えるようになったのはごく最近です。担ぎパスが苦手で、岩崎正寛さんの新作『三角潰しの法則』を見るまでスパーリングで試したこともほとんどないです。ディープハーフ、ラッソーもできません。できないことだらけですが、自分が戦える領域に閉じ込めてしまえばなんとかなります。
②ディフェンス力があれば何度もアタックできる
青帯1年目で悩んでいた時期に橋本知之さんの『ガードリテンション大全』(BJJ LAB制作)と『蹲踞ベース』(個人制作)で活路を見出しました。
(1)トップにおけるディフェンス力
蹲踞ベースのメリットは相手側の攻撃箇所を減らし、防御力を保ったまま攻撃できることです。機動力は劣りますが、安全に戦えるのでトップでの防御力に不安のある人にはおすすめです。
↓トップにとどまる時間が多いと、下の人がミスをしてくれたりします。
打込み練習会のテーマにもなった橋本知之さん(@tomohashi_ )の『蹲踞ベースシステム』教則。すごく使いやすい。(スタックからの展開はもっと慎重にしないと😅)
— ノブトウ (@nobutou) September 24, 2024
初対戦の相手など、情報がない場合でも安心して攻められる。ビビりな性格な僕にはぴったりのトップ戦略です💡 https://t.co/oDO7j1tjkA pic.twitter.com/GqeurZRFMC
(2)ボトムにおけるディフェンス力
ガードリテンション技術を身につけると、自分の時間が増えます。
『スラムダンク』という伝説的なバスケット漫画の一説に「リバウンド制する者、ゲームを制す」という言葉があります。

「リバウンド」とはリングに入らなかったボールを拾うことです。リバウンドができれば、-2点の劣勢から+2点のチャンスが生まれます。また優勢の場合は、リバウンドし続ければずっと+2点を狙えます。
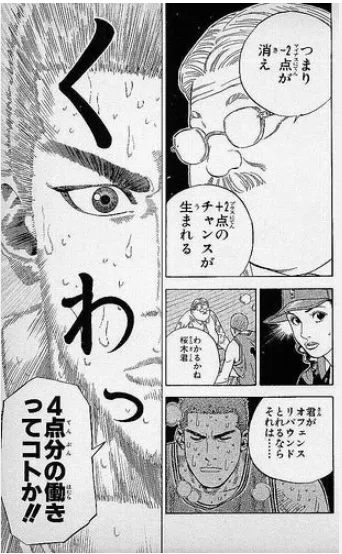
僕が所属するパラエストラ川崎の北出代表は「クローズドガードから腕十字を狙う場合、成功率10%でも問題ありません。 大切なことは、腕十字を失敗しても必ずクローズドガードに戻せること。10回狙えばいつか極まります」と言います。
トップにおいてもボトムにおいてもディフェンス力が上がれば、攻撃の時間が増えるので上達する方法も見えてきます。
③練習あるのみ。「いずれ上手くなる」と妄信する
やはり量です!(笑) 身も蓋もないですが。これは全帯に共通しています。
あらゆる競技に言えそうですが、習熟度が上がるにつれて「練習のたびに上手くなる」のではなく、「上手くなるヒントを引き出すために練習を続ける」ようになりそうですね👀
— ノブトウ (@nobutou) March 9, 2024
僕は中学までしかスポーツやってないので、そんなことは高校生でも知っとるわ、みたいなことを今から書きます笑…
青帯は一応「中級者の初歩」に分類されるので、練習すれば毎回上達を感じることは少なくなります。無意識に身に付くことはあるものの、意識的に「今日はこれを学んだぜ」と言えるものは少なくなります。
それでも練習を続けることが不安を解消する一番の方法です。
先月から柔術の停滞を感じて、今月は苦手なことだけ集中的に取り組む。白・青帯のメンバーにも結構やられて、キィーとなることもよくあった。ついに今日アハ体験みたいなものを得て、(手加減はあると思うけど)上の帯の人たちを攻め立てる動きができた。物事の上達はガタガタ階段状に進んでいくのだ💡
— ノブトウ (@nobutou) June 23, 2023
④負けても試合に出る。先生・先輩にアドバイスを受ける
個人的には一番これが良い方法でした。
青帯初期はたくさん負けましたが、負けを積み重ねることで強くなれました。試合についてアドバイスを求めると、先生や仲間も普段の練習以上に細かくアドバイスをしてくれます。
とはいえ、アドバイスを受けたのに同じミスを犯すなんてこともよくあります。それでも次に生かすためにもう一度チャレンジするしかありません。嘆いても技術にはつながりません。
⑤複数のガードやパスガードを試す
白青帯では試合で1つの得意ガードに特化した人の方が強いイメージです。
紫帯になると特化型の人は伸び悩んでいるように思います。というのも対策されるからです。実際に僕も特化型の人にはそのガードを作らせない動きを徹底して、自分の得意なポイントで戦うようにします。上手い紫帯の人はやはり2,3本の矢を持っています。
「柔術の全てのガードをやってみよう」みたいなことでもいいのではないかと思います。すぐに使える使えないは置いておいて。もしかしたら以前は苦手としていたものが一番の得意技になる可能性だってあるでしょう。
複数ガードを回していると少しずつ全体がレベルアップをしてきます。塗り絵感覚でやってみましょう。
柔術では体に合った技がいいと聞くけど、トップ選手でない限り自由でいいのでは?と思ってます。好きならガンガン打ち込みするし、派生する技も知りたくて知識も増える。
— ノブトウ (@nobutou) June 10, 2023
白帯時代やられまくりで萎えてましたが、デラ⇒ベリンボロを覚えて白帯と戦えるだけに留まらず、一気に青帯以上の人からバックを
⑥楽しいところにフォーカスする
結局、どんな競技も続けた人が勝つので、楽しみを見つけるのが大事です。
「できない・やられる自分は悪いんだ」だけになったらしんどいです。白帯の人から見ると、青帯になっている時点でめっちゃすごいことなんですが、青帯になると忘れてしまいます。
白帯の人にできないことの方が圧倒的に多いのです。
「まあ一つの趣味じゃん」くらいの割り切りを持ちつつ、うまくいかないことの方が多い中で楽しめる方法を見つけましょう。
楽しみを見つけるとは?
「経験者はよく『もっと楽しもう』と言うけれど、やられてばかりで楽しくない」
という方も多いでしょうか? そういう方はハードルをもっと下げるしかありません。
一例ですが、僕は教則やクラスで習ったテクニックを『試す』ことを楽しみにしています。試すことが目的なので、それが有効にかからなくてもOKとしています。
しんどいスパーの中で、事前にテーマとして決めたテクニックにチャレンジしただけで自分を褒めるようにしています。
某氏の教則にある場面になり「奥足を掴むパターンだと手のラインを超さないと相手が立つと押さえ込まれる?」→「逆足でキックだったよな?」→「いや逆か?」とモタモタしてスイープ。で、帰って教則を見返すと重要な細部が違っていた💣 教則やクラスのテクを試している時が一番楽しい。 pic.twitter.com/0IhU8ir8R2
— ノブトウ (@nobutou) February 18, 2025
楽しみ方はそれぞれです。最近はBJJ LABのYoutubeで『ノブトウさん改善企画』をやっていて、試合の目的はこれになっています。
試合に勝つことも大事ですが、試合の中でBJJ LABの教則や竹浦さんに教わったことにチャレンジしたらそれをゴールとします。
柔術は考えることで強くなる
— 竹浦 正起 Takeura Masaki™️ (@MasakiTakeura) March 15, 2025
柔術ではフィジカル的な強さ以上にロジカルな思考を持って、テクニックを駆使して戦うことが強さにつながる。柔術において「考える」ことは重要だ。
私は柔術において考えることを大事にしています。… pic.twitter.com/MjlYQx2xHk
⑦記録をつける
記録をつけることも楽しみにしています。ルールは「1日の練習で1つだけ学ぶポイントがあればOK」としています。
これも⑥と同じで、学べたかが大事で、うまくいったかどうかはどちらでもよしとしています。
練習前には3つくらいやるべき課題を決めてスパークラスに臨むわけですが、疲れたり、使える状況がこなくて3つはできないことが多いです。でも3つあれば1つは何かしらそういった状況が来ます。
1つを記録して覚えておけば月に10個は学べるわけです。

青帯で1,2年が経つと紫帯の人と十分戦える
青帯になってちょうど2年が経ちました。試合での勝率も上がり、紫帯の人たちを抑え込む機会も増えました。
白帯の頃は雲の上の存在に感じていた紫帯の人たちと組み合えるので、柔術はおもしろいです。
柔術を始めた当初は紫帯ってめちゃくちゃ上の存在に感じていたけど(黒帯との違いもわからないくらい)、徐々に近づいてきた実感はある。
— ノブトウ (@nobutou) November 16, 2024
一方、当初の想定外だったことは青帯アダルトの上位層がめっちゃ強いこと笑 マスターで茶帯くらいにならないと勝てなさそう。とりあえずもう一本青帯買おっと。
青帯になった当初は「攻撃パターン1つしかないけど大丈夫かな?」と思ってましたが、ある程度上達してくると大半の青帯が1,2パターンしか持ってないことに気づいて安心します←安心してる場合ではない笑
— ノブトウ (@nobutou) January 15, 2024
紫帯になると攻撃力・パターンはまちまちですが、防御力は青帯より1段階あがるなと感じます。 https://t.co/p8BiAO1nZi
上達のコツを意識してからずっと伸びている
青帯になりたての頃は「練習を続けるにつれて成長が鈍化していくんだろうな」と不安に思っていましたが、練習方法を工夫したり試合に出続けることで、練習量に比例して上達するようになりました。
よくよく考えると、伸び悩みを感じた時期はデラヒーバで展開を作るだけでした。今はハーフ、スパイダー、シャローラッソーもそこそこ使えます。ラペラを使ったガードも試しています。柔術のカラフルさを楽しめることで全体のベースアップもできています。
逆に「これはしない方が良い」と思うこと
全体的に見ると成長していく青帯が多いですが、青帯の2年目を迎えてもあまり成長していない人もいます。反面教師的な情報もあった方がいいと思うので書いておきます。おそらくあなたのジムにもこんな人がいるんじゃないでしょうか?
1.試合に出ない/出なくなる
青帯になって試合に勝てなくなるとおもしろくなくなります。かといって試合に出ないと上達は速くなりません。悪いサイクルに入ります。
「試合に出なくても上達する」という上級者はたくさんいますし、それ自体は否定しませんが、成長速度は絶対に上がりません。
上達が遅くなれば、そのぶん楽しむ速度も減ります。早く上達したいなら試合は必須ツールです。
出場数に比例して上達するわけではありませんが、一定のペースで試合にエントリーしてそこに合わせて自分の技術を点検することが重要になります。blue belt bluesから抜け出したいなら、年に1,2回は出場すべきと考えます。
先日青帯1年目の仲間に「連敗していて、次試合のエントリーを躊躇する」と話しかけられました。「負け癖がつくからよくないと言いますし」とのこと。これは難しいですね。もしかしたら僕も負け癖がついているかもしれないので笑、良いアドバイスが浮かびませんでした。…
— ノブトウ (@nobutou) March 11, 2025
2.自分より未熟な相手に得意技を掛け続ける
得意技の精度をさらに上げていく練習は必要ですが、同じ相手に同じポジションから何度もかかるのであれば、それ以上の反復はあまり意味がないのではないかと思います。
それならその人に自分の戦略やどう防げばいいかを教えてあげて、それをさらに崩す練習をする方がお互いのためになります。
3.自分の苦手なポジションやガードに目を向けない
これは僕もしばらくできていませんでした。練習テーマを決めずに惰性でジムに行き、組み合うといつも同じガードをやっているということはよくありました。これは練習前のメモを読み返すだけで改善できるので、ぜひやってみてください。
4.新しい知識を得ない
これはポジショントークと思われるかもしれませんが、上手い人は教則を見ています。ビジネスマンはたくさんクラスに出る時間はないはず。クラスには場所的・時間的な制限があります。Youtubeの無料動画や試合動画を見ることでも上達にはつながると思うので、ぜひじっくり見ていきましょう。
どの帯でも段階に応じたしんどさがある
先日こんな投稿を見かけました。紫帯でも苦悩はあるそうです。
柔術、青から紫に上がったタイミングで明確に挫折している。今もそれは続いている。柔術がそんなに好きじゃないかもって思い始めていることと、すべてを覚えようと思うには広大過ぎること、一方でこのルールでしか使えないこともまた多い。俺の柔術に何が必要か教えて欲しいなぁ。
— あぶてん (@abtn1111) March 15, 2025
僕はまだ青帯ですが、紫帯→茶帯のレベル差について感じることが多いです。
これは現在黒帯の方の投稿。
俺のポテンシャルだったらこの辺が限界で、これ以上はどうやっても強くなれないだろうなと青や紫の頃に何度も思ったことがあります。
— 武元【腕十字Lv.1】 EXP:31P (@T_STYLE_Axis) March 17, 2025
こちらはBJJ LABからラペラガードの教則を提供いただいている高橋謙人さんの投稿。
今週末のSJJJF九州国際柔術オープンのトーナメント発表されました。
— 高橋謙人 Kento Takahashi⬛️🟥⬛️ (@kento_cdbjj) December 8, 2022
1回戦から韓国🇰🇷の選手との対戦で国際大会の名に相応しい組み合わせに…。
九州のベテラン、若手黒帯揃い踏みでプロシューター、現役全日本王者など錚々たるメンツの中に僕みたいな黒帯1年生が挑戦です!
応援宜しくお願いします! pic.twitter.com/Abx68JmSXS
黒帯もしんどさがあるそうです。黒帯になってしまうと、次の目指す帯は実質ありません。試合においては強さの上限がなくなります。黒帯1年目なのにキャリア20年の黒帯と戦うこともあるでしょう。
SNSでよく見かける“紫帯が1番楽しい”って自分が紫帯に昇格した時にもある有名な黒帯の方にそういうコメントを頂いた。
— 高橋謙人 Kento Takahashi⬛️🟥⬛️ (@kento_cdbjj) January 31, 2025
白、青まではわからない事だらけ。
茶、黒は足関節の種類も増えるし、そもそも試合相手もなかなか居ない。
紫帯はちょうどその中間地点。
ある程度技術も付いて、試合相手も多い。
黒帯になっても苦悩は続くようです。紫帯・茶帯にもレベルに応じた悩みはあると言えます。
ずっと苦悩し続ける競技なのかもしれません。
上達しないとおもしろくない
柔術はいろんな楽しみがあります。でも共通するのは上達しないとおもしろくないということです。
どうすれば上達するのか? 量と質を高めていくしかありません。これも全帯共通ですね。
白帯、青帯でしんどい方はぜひBJJ LABの作品や『マスター世代の上達を科学する』(Youtube企画)を見てみてください。きっと良い発見があります。
僕は一競技者として、また教則制作のチームの一員として、皆さんの柔術ライフの一助になれるようにがんばります。
引き続きよろしくお願いします。最後まで読んでいただきありがとうございます。